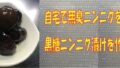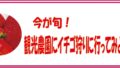春の七草でつくる七草粥ってどの様なもの?
お正月明けにスーパーなどでよく見かける「春の七草」と使った七草粥はどのような歴史や味がするのか興味をもち早速材料を調達して作ってみることにしました。
七草粥の発祥は?
どうして出来たの?・・・七草粥は奈良時代にさかのぼります。そして平安時代に宮中に提供される行事に供され後、江戸時代になり幕府の行事の一部に成りました。その後明治時代になり暦の改正が実施され旧暦が廃止され新暦になりましたがこの風習が民間に引き継がれ現在に至ります。一年の無病息災を願って食べるシンプルな粥を言います。
入れる春の七草とは?・・・
芹(セリ)、薺(ナズナ)、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、鈴菜(スズナ)、蘿蔔(スズシロ)をあらかじめ準備しておきます。今ではスーパーでもセットしたパックが販売されています
薺(ナズナ)・・・あらゆるものを撫でて汚れをとり除くさま
ゴギョウ・・・仏の姿
ハコベラ・・・永遠に繁栄がはびこるように願う
ホトケノザ・・・仏が座っている場所
鈴菜(スズナ・・・幸運を呼び寄せる神様を呼ぶ鈴
蘿蔔(スズシロ)・・・汚れのない清らかな白
春の七草は薬草ですか?
春の七草は、薬草としても利用されることがありますが、主に日本の伝統行事「七草粥(ななくさがゆ)」に関連した草です。この七草は、一般的に春の訪れを感じるために食べられ、また、健康を願って食べる習慣があります。
春の七草は以下の通りです:
- セリ(芹) – 消化を助け、血行促進作用があるとされています。
- ナズナ(薺) – 別名「ぺんぺん草」で、解毒作用や利尿作用があるとされています。
- ゴギョウ(御形) – 別名「母子草」で、風邪や咳に効くとされています。
- ハコベラ(繁縷) – 血行を良くする作用があり、体力回復に良いとされています。
- ホトケノザ(仏の座) – 食欲を増進させる効果があるとされています。
- スズナ(蕪) – 消化を助け、便通を良くする作用があります。
- スズシロ(大根) – 解毒作用や消化を促進する効果があります。
これらの草は、薬草としても古くから利用されており、特に体調を整える効果が期待されています。しかし、現在では主に七草粥を食べて新年の無病息災を祈るための行事として親しまれています。
いつ食べるの?
1月7日の朝に食べます。
入れる七草は地域で違いはあるの?
七草粥は、日本各地で地域の特色を反映したバリエーションがあります。以下、いくつかの地方の特徴を紹介します。
1. 関東地方(一般的な七草粥)
七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、スズシロ(ダイコン))を入れた、シンプルな塩味の粥が主流です。
2. 関西地方(味付けや具材に特徴)
関東と同じ七草を使いますが、だしを効かせたり、味噌を加えることもあります。また、京都では「白味噌仕立て」の七草粥が食べられることもあります。
3. 東北地方(餅や小豆入り)
寒冷地のため、七草の代わりに野菜や餅を入れることが多いです。特に、青森県や岩手県では「小豆粥(小豆を炊き込んだ粥)」を食べる風習もあります。
4. 北陸地方(海藻入り)
石川県や富山県では、七草の代わりにワカメや昆布を入れることがあり、海の幸を活かした七草粥になります。
5. 中国・四国地方(魚や雑炊風)
岡山県では「ばら寿司」に使われるような具材(魚や野菜)を入れることもあります。また、香川県ではいりこ出汁を使って風味豊かに仕上げることがあります。
6. 九州地方(具だくさん)
大分県では鶏肉やゴボウを加えた七草粥が作られることもあります。福岡県では高菜や青菜を加えて食べることがあり、栄養価が高くなっています。
7. 沖縄地方(ジューシー)
沖縄では七草粥の代わりに、**「ジューシー」(沖縄風炊き込みご飯)**を食べることもあります。沖縄の伝統的な薬草(フーチバー=ヨモギなど)を加えることが多いです。
このように、地方ごとに特色があり、七草粥も地域の食文化と結びついているのが面白いですね!
食べる日の違いはあるの?
春の七草を食べる日には一般的な1月7日と、地域によって異なる1月15日などがあり、地域の文化や習慣によって異なることがあります。これらの違いは、地域の風習や農業のリズムに根ざしていることが多いです。
七草粥の効用は?
お正月にたくさんのご馳走は召し上がって疲れた胃を休める意味でも最適かもしれません。胃を丈夫にする効果や利尿作用や食欲増進効果、血圧を下げる効果、胃腸障害やむくみ解消効果が有ります。詳しくは次の通りです
- 消化促進: 七草には食物繊維が豊富に含まれており、消化を助ける効果があります。
- 栄養補給: 七草はビタミンやミネラルが豊富で、体に必要な栄養素をバランスよく摂取できます。
- 免疫力向上: ビタミンCや抗酸化物質が含まれており、免疫力を高める効果があります。
- デトックス効果: 七草には利尿作用があり、体内の余分な水分や老廃物を排出する助けになります。
- 疲労回復: 栄養価が高く、エネルギーを補給することで疲労回復に寄与します。
- 風邪予防: 免疫力を高めることで、風邪やインフルエンザの予防に役立ちます。
- 血行促進: 七草に含まれる成分が血行を良くし、冷え性の改善に寄与します。
- 美肌効果: ビタミンやミネラルが肌の健康を保ち、美肌効果が期待できます。
- ストレス軽減: 温かいお粥は心を落ち着け、リラックス効果があり、ストレス軽減に役立ちます。
- 無病息災の願い: 七草粥を食べることで、無病息災を願う伝統的な意味があり、心の健康にも寄与します。
これらの健康効果により、七草粥は新年の行事としてだけでなく、日常的にも健康を意識した食事としておすすめです。
味はどんな感じ?
うすい塩味に成ります。濃い味に慣れた現代社会人には物足りなさを感じるかもしれませんが、一年に一度は身体を労わる意味でも食されては如何でしょうか?
ご飯 2杯分
水 6カップ
塩(ミネラルが多く含む粗塩が最適です)少々
七草
本だし(顆粒) 小さじ2杯
①鍋にごはん・水・塩を入れて約10分間煮る
②七草はあらかじめ軽く塩ゆでして冷水で締めておく(みどりが鮮やかになり食欲をそそります!)
③塩ゆでした七草をみじん切りにして本だしを加えます。
④調理した七草を①のごはんを混ぜて軽く煮ます。これで出来上がり!
(調理時間) 約20分
まとめ
七草粥は若草を食する風習は中国から伝わったとされ日本では古くは奈良時代から平安、江戸、明治の変遷を経て今に引き継がれています。まさに伝統的な食べ物と言えます。
人々の無病息災や健康を願って食べるシンプルな塩味の粥です。この七草粥は全国各地で多用な食材を用いられ食される日も色々違いがみられますが飽食の時代を生きる私達に一服の清涼剤に成りうる食材だと思われます。